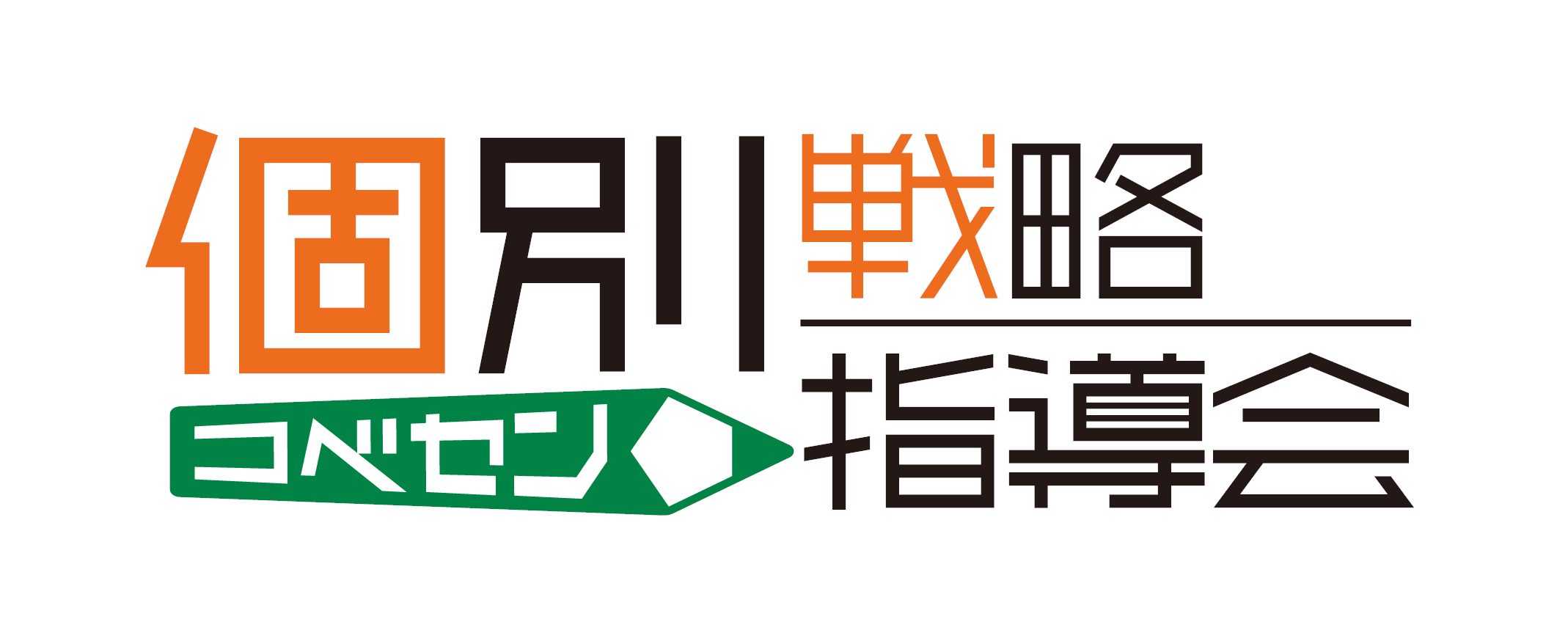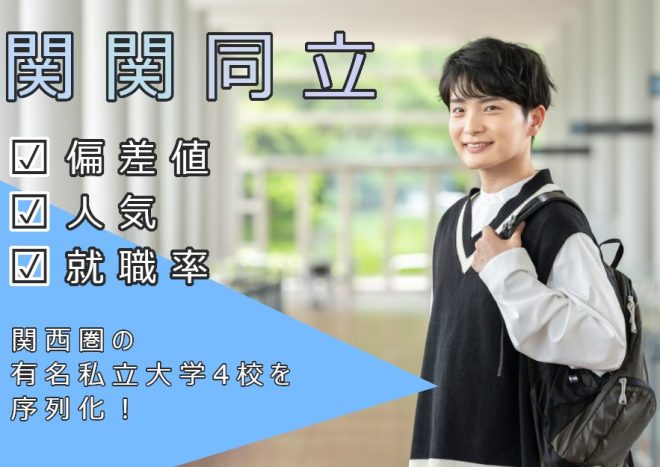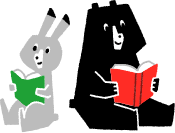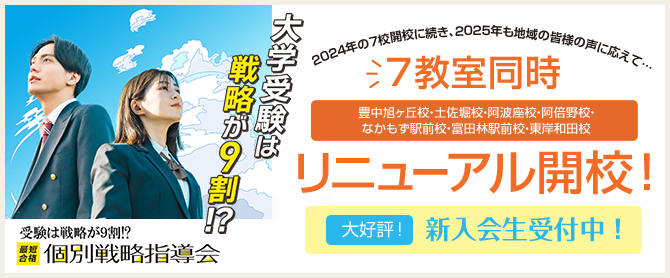産近甲龍の共通テスト利用入試を徹底解説!学部ごとの得点率やメリット・デメリットなど

「産近甲龍を共通テストを利用して受験する場合、どのくらいの得点が必要か気になる」
「共通テストを利用して受験する際のメリットやデメリットを詳しく知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
関西地方で人気の準難関私立大学群「産近甲龍」では、共通テストを利用した受験が可能です。そのため、共通テストを活用して産近甲龍を目指す方も少なくありません。
この記事では、産近甲龍の共通テスト得点率や受験時のメリット・デメリットなどを解説します。
さらに後半部分では、共通テストで産近甲龍の合格率を上げるポイントやよくある質問も紹介するので、最後までご覧ください。
あなただけの戦略で国公立・関関同立合格を目指す!
大学受験 個別戦略指導会

この記事のポイント
大学入試の共通テスト利用入試とは?
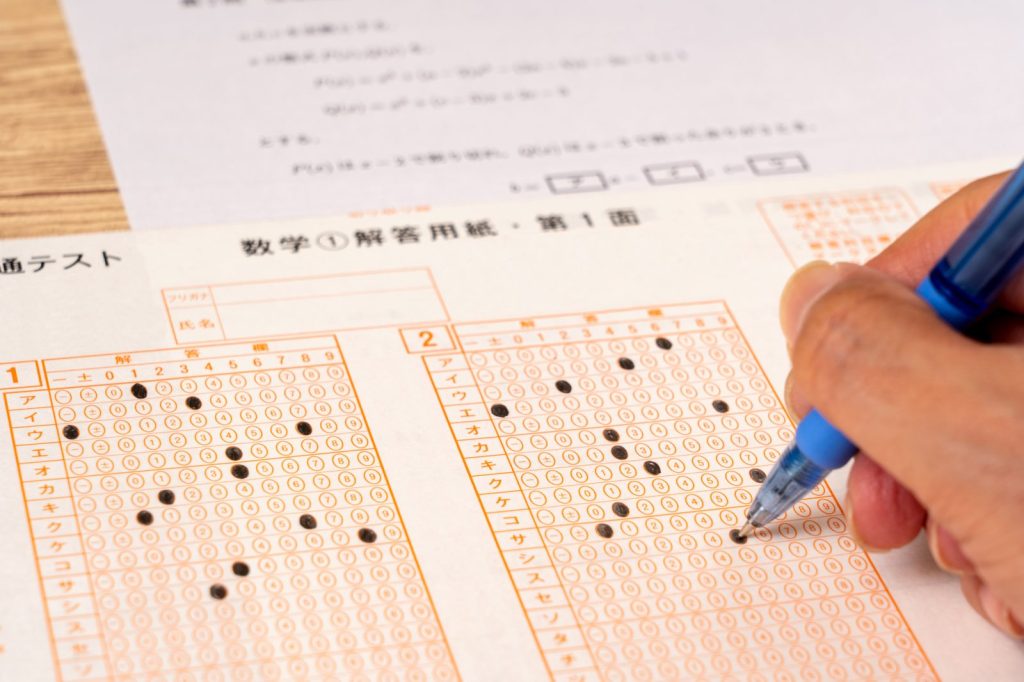
共通テスト利用入試は、大学入試共通テストの成績をもとに合否を判定する入試方式です。
主に私立大学で採用されており、以下のような特徴があります。
- 複数大学に出願可能:共通テストの成績で複数の大学に出願できます。
- 受験料が安い:一般入試と比べて受験料が安くなります。
- 早い入学手続き:入学手続きの日程が早めに設定されている場合が多いです。
一般入試は1回の受験でひとつの学部のみ合否判定が行われます。一方で、共通テスト利用入試では、共通テストを利用して複数の大学に出願することが可能です。
また、一般入試では1回の受験につき約3万円の費用がかかりますが、共通テスト利用入試では、2科目で1万2,000円、3科目以上でも1万8,000円程度で済むケースが多いです。
このように、一般入試と比べて受験料の負担が軽いことも共通テスト利用入試の大きなメリットといえるでしょう。
産近甲龍の共通テスト得点率

それでは、産近甲龍の共通テスト得点率から確認していきましょう。
共通テスト利用入試で受験する際は、各大学の共通テスト得点率を超えることを目標にしてください。
京都産業大学の共通テスト得点率
京都産業大学の共通テスト得点率は、59〜72%です。
全体的な得点率は低めで、産近甲龍の中でも共通テスト利用入試で合格しやすい大学と言えます。
学部ごとの共通テスト得点率・偏差値は、以下の通りです。
| 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 64~68% | 53~57 |
| 経営学部 | 64~67% | 53~56 |
| 法学部 | 64~65% | 51~55 |
| 現代社会学部 | 63~72% | 52~58 |
| 国際関係学部 | 61~67% | 51~56 |
| 外国語学部 | 60~62% | 47~57 |
| 文化学部 | 62~69% | 51~56 |
| 理学部 | 59~71% | 49~57 |
| 情報理工学部 | 66~72% | 53~56 |
| 生命科学部 | 61~67% | 50~54 |
参照:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/school/3594/hensachi/index.html
文系学部は他大学と比較して得点率が5~10%ほど低く、狙いやすい学部が多くあります。
一方で、理学部や情報理工学部などの理系学部は得点率が高めで、難易度がやや上がる傾向があります。
近畿大学の共通テスト得点率
近畿大学の共通テスト得点率は、49〜87%です。(※薬・医学部を除く)
近畿大学は産近甲龍の中でも特に人気が高く、そのため共通テスト利用入試における得点率も全体的に高い水準となっています。
学部ごとの共通テスト得点率・偏差値は、以下の通りです。
| 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法学部 | 72~85% | 59~63 |
| 経済学部 | 65~84% | 57~65 |
| 経営学部 | 66~79% | 56~63 |
| 理工学部 | 69~84% | 52~58 |
| 建築学部 | 77~84% | 59~60 |
| 文芸学部 | 67~86% | 55~64 |
| 総合社会学部 | 70~87% | 58~67 |
| 国際学部 | 63~72% | 56~64 |
| 情報学部 | 75~84% | 56~60 |
| 農学部 | 65~81% | 53~61 |
| 生物理工学部 | 50~72% | 48~53 |
| 工学部 | 63~82% | 47~56 |
| 産業理工学部 | 49~79% | 47~54 |
参照:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/school/3647/hensachi/index.html
近畿大学の共通テスト利用入試では、文系・理系を問わず70%前後の得点率が合格の目安となることが多いです。
特に、建築学部や情報学部は得点率が高いため、難易度も相対的に高くなっています。
一方で、農学部や理工学部の一部は得点率が比較的低めに設定されており、合格を狙いやすい学部といえるでしょう。
甲南大学の共通テスト得点率
甲南大学の共通テスト得点率は、49〜82%です。
産近甲龍の中でも、甲南大学は全体的に得点率が高い傾向にあります。
学部ごとの共通テスト得点率・偏差値は、以下の通りです。
| 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 文学部 | 55~82% | 55~66 |
| 経済学部 | 70~74% | 57~63 |
| 法学部 | 49~77% | 53~61 |
| 経営学部 | 67~81% | 55~62 |
| マネジメント創造学部 | 67~72% | 53~59 |
| グローバル教養学部 | – | 56~57 |
| 理工学部 | 63~74% | 50~55 |
| 知能情報学部 | 63~68% | 51~57 |
| フロンティアサイエンス学部 | 62~76% | 50~58 |
参照:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/school/3696/hensachi/index.html
甲南大学では、多くの学部で60%以上の得点率が求められるため、近畿大学や龍谷大学に比べて合格しやすい学部は少ない傾向にあります。
特に、経済学部は得点率が70~74%と高く、しっかりとした共通テスト対策が必要です。
一方で、学部によっては偏差値や得点率に幅があるため、自身の得意科目や得点配分に合わせて戦略的に選ぶことが重要です。
龍谷大学の共通テスト得点率
龍谷大学の共通テスト得点率は、50〜84%です。
龍谷大学は、産近甲龍の中でも幅広い学問分野を提供しており、学部ごとに求められる得点率に差があるのが特徴でしょう。
学部ごとの共通テスト得点率・偏差値は、以下の通りです。
| 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 心理学部 | 64~76% | 60~64 |
| 文学部 | 50~84% | 45~67 |
| 経済学部 | 57~72% | 54~61 |
| 経営学部 | 64~70% | 52~61 |
| 法学部 | 64~74% | 55~62 |
| 政策学部 | 60~73% | 52~59 |
| 国際学部 | 57~78% | 53~60 |
| 先端理工学部 | 52~72% | 48~54 |
| 社会学部 | 58~75% | 53~60 |
| 農学部 | 57~69% | 48~54 |
参照:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/school/3609/hensachi/index.html
龍谷大学は、学部によって共通テスト得点率に大きな差があります。
例えば、心理学部心理学科は64〜76%の得点率であるのに対し、先端理工学部の環境科学課程では52~72%と、学部によって難易度が異なるのが特徴です。
その他の学部は、他大学と比較してもおおむね平均的な難易度といえるでしょう。
あなただけの戦略で国公立・関関同立合格を目指す!
大学受験 個別戦略指導会

産近甲龍で共通テスト利用入試を受験するメリット

共通テスト利用入試は、産近甲龍の各大学において広く採用されており、受験生にとって非常に効率的な入試方式です。
ここからは、産近甲龍で共通テスト利用入試を受験するメリットを3つ解説します。
1. 複数の大学を併願できる
産近甲龍で共通テスト利用入試の最大のメリットは、一度の試験で複数の大学に出願できることです。
産近甲龍の各大学では共通テストのスコアを利用して受験する方式が用意されているため、気になる大学・学部が複数ある場合は同時に合格を狙えます。また、学部・学科ごとに科目や配点が異なるため、自分の得意科目を活かして出願先を選ぶことも可能です。
また、共通テストの成績を使って判定を受けるため、試験日程が重複しない点も大きな利点でしょう。
2. 受験料が安い
共通テスト利用入試は、受験料が一般入試よりも低く抑えられている点も魅力です。
一般入試では1つの学部につき約3万円の受験料がかかりますが、共通テスト利用入試では1回の受験で済むため、費用負担が軽減されます。具体的には、産近甲龍の共通テスト利用入試の場合、1出願あたり平均15,000円程度と、一般入試に比べて費用を抑えることができます。
さらに、一度受験した共通テストの成績を利用できるため、追加の試験費用が不要になります。
経済的な負担を軽減しながら、複数の大学にチャレンジできるのは大きなメリットでしょう。
3. 一般入試との併願が可能
共通テスト利用入試は、一般入試と併願できる点も大きなメリットです。
共通テストの結果が思うように振るわず、共通テスト利用入試で不合格となった場合でも、一般入試を受けて挽回するチャンスがあります。一般入試に絞った場合は1回限りの挑戦となりますが、共通テスト利用入試と併願することで、受験のチャンスが2回になるため、心理的な安心感も得られます。
また、共通テスト利用入試で第二志望を確保しつつ、一般入試で第一志望を狙うといった柔軟な戦略を立てることも可能です。このように、共通テスト利用入試と一般入試を組み合わせることで、リスクを分散しながら効率的に受験を進められるでしょう。
産近甲龍で共通テスト利用入試を受験するデメリット
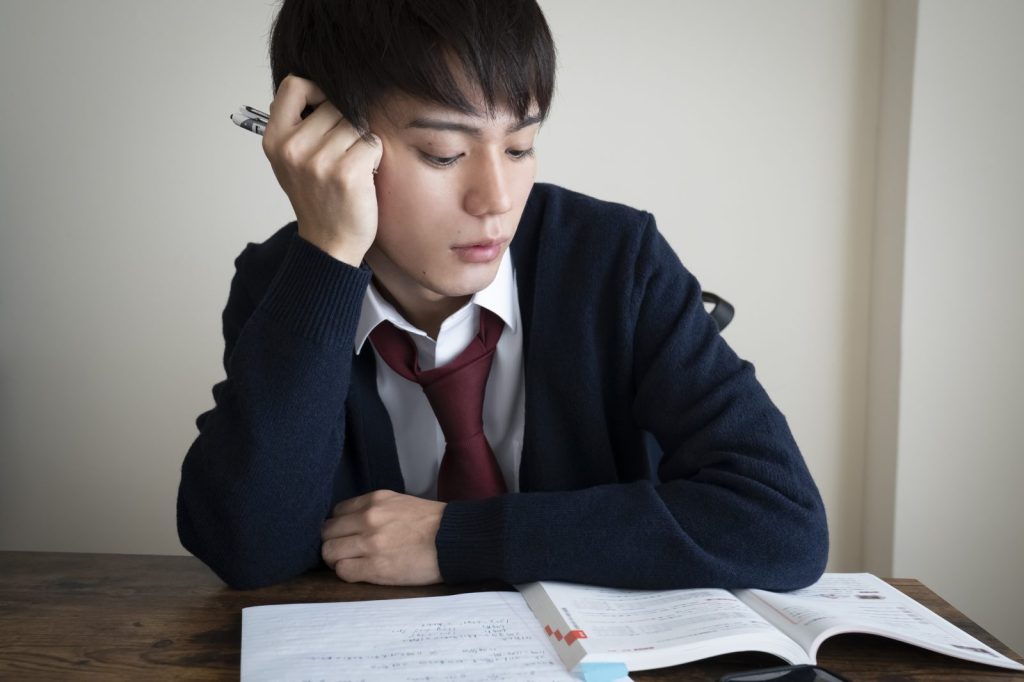
共通テスト利用入試は多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
ここでは、産近甲龍で共通テスト利用入試を受験するデメリットについて解説します。
1. 一般入試よりも合格難易度が高い
産近甲龍で共通テスト利用入試を受験する1つ目のデメリットは、一般入試よりも合格難易度が高いことです。
共通テストは主に国公立大学志望の生徒が受験する試験です。そのため、国公立志望の生徒が滑り止めとして関関同立や産近甲龍にも出願するケースが多く、競争率が上がる傾向にあります。
その結果、産近甲龍の中でも人気学部では、高得点が必要になることが珍しくありません。
一方で、一般入試では学部ごとの個別試験があるため、得意科目を重視した出題や出題傾向への対策ができる分、共通テスト利用入試に比べて戦略が立てやすい場合もあります。
共通テスト利用入試を検討する際は、得点率の基準や自身の成績を考慮したうえで慎重に判断することが重要でしょう。
2. 勉強すべき受験科目が増える
産近甲龍で共通テスト利用入試を受験する2つ目のデメリットは、勉強すべき受験科目が増えることです。
一般入試では通常、英語・国語・数学の3教科で受験できることが多いですが、共通テスト利用入試では5教科7科目が必要になる学部もあります。これにより、対策すべき科目数が増え、受験生にとっての負担が大きくなる可能性があります。
特に、普段あまり勉強していない科目も含めて幅広く対策を行う必要があるため、計画的なスケジュール管理が求められます。
その場合は、学習塾や予備校などでプロのアドバイスを受けながら効率的に学習を進めることが、科目数の増加による負担を軽減するポイントとなります。
3. 共通テスト利用入試後に一般入試対策に切り替える必要がある
3つ目のデメリットは、共通テスト利用入試後に一般入試対策へ切り替える必要があることです。
仮に共通テスト利用入試で合格を確保できなかった場合、直後に一般入試対策へ集中する必要があります。
共通テストでは標準的な問題が出題される一方、各大学の一般入試では、大学ごとの特色が反映された問題が出されます。そのため、問題の形式や特徴に慣れていないと、思うように得点できず不合格となるケースもあります。
さらに、共通テスト利用入試で不合格となった場合、精神的なダメージを受けてしまい、一般入試に向けた勉強に集中できなくなるリスクもあります。受験スケジュールを立てる際は、精神的なケアや万が一の場合に備えたプランを考えておくことが大切でしょう。
共通テスト利用入試で産近甲龍の合格率を上げるポイント

「国公立志望の受験生が滑り止めとして受験する産近甲龍に、共通テスト利用入試で本当に合格できるのか不安…」と感じる方も多いかもしれません。
この項目では、共通テスト利用入試で産近甲龍の合格率を上げるポイントを3つ解説します。
1. 受験科目の基礎学力を上げる
共通テスト利用入試で産近甲龍に合格するための最も基本的な方法は、受験科目全体の基礎学力を底上げすることです。
共通テストでは、基礎的な内容が幅広く出題されるため、まずは中学レベルの知識からしっかりと復習して土台を固めることが重要です。例えば、英語であれば、以下のステップで学習を進めると効率的です。
1. 中学レベルの単語・文法を復習する
2. 中学3年間の総まとめとして長文読解に取り組む
3. 高校レベルの単語・文法を学習する
4. 高校レベルの長文読解に進む
また、定期的に過去問や模試を解き、得点率の目標と現在のスコアを比較しながら学習を進めることで、弱点を把握し、効率よく基礎力を向上させることができます。
2. 得意科目を活かせる方式を選ぶ
2つ目のポイントは、自分の得意科目を最大限活かせる方式を選ぶことです。
産近甲龍の共通テスト利用入試では、大学や学部ごとに必要な科目や配点が異なります。そのため、出願前に各大学の入試方式を詳しく調べ、自分に有利な方式を選ぶことが合格率アップの鍵となります。
例えば、龍谷大学先端理工学部環境学科の「前期併用2科目方式」では、数学、社会、理科の中から得意な2科目を選んで受験できるため、理系科目が得意な受験生にはおすすめです。このように、得意科目が高配点になる学部や方式を選ぶことで、他の受験生と差をつけやすくなります。
事前に大学ごとの出題傾向や配点を確認し、自分の得意分野を活かせる出願先を選びましょう。
3. 共通テスト得点率の低い学部を狙う
3つ目のポイントは、共通テスト得点率の低い学部を狙うことです。
国公立志望の受験生が滑り止めとして選ぶ傾向が強い人気学部を避け、得点率が比較的低い学部に出願することで、合格しやすくなります。
例えば、龍谷大学文学部歴史学科(日本史学専攻)は共通テスト得点率が約75%と高めですが、同じ大学の先端理工学部環境科学課程では得点率が約60%となっています。同じ大学内でも学部によって15%ほどの差があることも珍しくありません。
得点率が低めに設定されている学部を狙うことで、合格の可能性を広げることができます。志望校や学部選びの際は、志願者動向や得点率を十分にリサーチし、戦略的に出願を検討しましょう。
産近甲龍の共通テスト利用入試に関するよくある質問

ここでは、産近甲龍の共通テスト利用入試に関するよくある質問を2つまとめました。
- 共通テスト利用入試と一般入試の違いはなんですか?
- 一度に複数の学部や大学に出願できますか?
それぞれ回答していきます。
共通テスト利用入試と一般入試の違いはなんですか?
試験内容や受験科目、試験日程など、さまざまな違いがあります。
詳細は、以下の比較表をご覧ください。
| 共通テスト | 一般入試 | |
|---|---|---|
| 試験形式 | マークシート | 大学独自の試験内容 |
| 試験科目 | 7教科21科目から選択 | 大学独自の試験科目 |
| 試験日程 | 毎年1月中旬の土日 | 大学独自の日程 |
| 受験機会 | 1回 | 複数回受験可能 |
| 受験料 | 2教科以下:1万2,000円 3教科以上:1万8,000円 | 1回3万円前後 |
一度に複数の学部や大学に出願できますか?
共通テスト利用入試では、一度の試験結果を使って複数の学部や大学に出願することが可能です。
共通テストの成績は共通の基準で評価されるため、1回の試験結果を基に、産近甲龍の各大学・学部へ同時に出願できます。
ただし、各大学や学部で必要な科目や配点が異なるため、出願先に応じた科目選びが重要です。また、出願にはそれぞれの大学の受験料が必要なので、事前に費用を確認しておきましょう。
あなただけの戦略で国公立・関関同立合格を目指す!
大学受験 個別戦略指導会

まとめ
この記事では、産近甲龍の共通テスト得点率やメリット・デメリット、合格率を上げるポイントなどを解説しました。
産近甲龍は関西圏で多くの受験生から支持される準難関私立大学群であり、その知名度から、毎年多くの志願者が集まります。そのため、入試の難易度も決して低くはありません。
「国公立志望勢が流れてくる共通テスト利用入試では、合格は難しい」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際には共通テスト得点率が低く設定されている学部を狙うことで、一般入試よりも難易度が下がるケースも多々あります。
また、共通テスト利用入試は、複数大学への併願が可能であることや、一般入試と比較して受験費用を抑えられるメリットもあります。
産近甲龍を目指すなら、共通テスト利用入試を賢く活用し、志望校合格への道を切り開いてください。